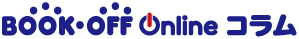須賀しのぶ『革命前夜』は、歴史・音楽好き必読の書!
更新日:2016/6/14
『革命前夜』
須賀しのぶ(著)、文藝春秋
2016年の第18回 大藪春彦賞受賞作品である、須賀しのぶさんの『革命前夜』。
この作品は、冷戦下の東ドイツに留学した日本人ピアニストの視点から、激動の時代の人々の生き方を描く歴史エンターテイメント小説です。
東西に分かれてしまったドイツ、その東側の人々が、悩みや苦しみを抱えながらも自分の生きる道を選び取っていく物語が描かれます。
主人公はピアニストで、舞台も主に音楽大学を中心として進んでいくので、クラシック音楽、特にバッハが好きな方にもおすすめです。
バッハに憧れ、東ドイツへ留学した主人公

物語の始まりは、昭和が終わり平成が始まるまさにその日。主人公の眞山柊史(まやましゅうじ)は、ドレスデンの音楽大学に入学するために東ドイツへやってきました。
留学先に東ドイツを選んだ理由は、主人公はバッハを敬愛していたからです。
バッハの音楽に魅せられた眞山は、
「彼を育んだザクセンの空気の中でただひたすらピアノに向き合いたい。」(p.8)
と願っていました。
しかし、せっかく東ドイツへの留学を果たしたものの、眞山は深刻なスランプに陥ってしまいます。全く音が響かなくなり、ホームシックにまでかかってしまいます。
そんなとき、気分転換にと街へ連れ出された眞山は、ジルバーマンのオルガンを見るために旧宮廷教会を訪れます。そこでは、金髪の美しい女性がオルガンを奏でていました。
眞山は、その音色にすっかり心を奪われてしまい、もう一度彼女に会いたいと願うようになります。
どこか影のあるオルガニスト・クリスタと、自由奔放なヴァイオリニスト・ヴェンツェルとの出会い

大学で、眞山は北朝鮮からの留学生の李や、ヴァイオリン科の優等生、イェンツとそのパートナーであるガビィなど、何人かの学生たちと交流を持つようになります。
特に強烈なのが、ハンガリー出身の留学生、ヴァイオリン科のヴェンツェルです。
眞山はヴェンツェルになかば強引に学内演奏会での伴奏を引き受けさせられ、他人の感情をくみとることない彼の行動や言動、そして自由奔放すぎる音楽に振り回される日々を送ります。
彼と練習を始めて、僕は一日たりとも怒りを感じない日はなかったが、心のどこかで、今日はどんなふうに引きずり回してくれるのかという期待もあった。腹を立てながら、昨日までそこにあったものが一瞬にして破壊され、瞬く間にまるで違うものに再構成されていく様に、ぞくぞくしていた。(p.44)
そしてついに演奏会の舞台に立ったその日、眞山は観客席である1人の女性を見つけます。それは、あの旧宮廷教会でオルガンを弾いていた、金髪の美女でした。
いたるところに「監視者」がいる社会

金髪の天才オルガニスト、クリスタとの出会いによって、眞山は東ドイツの現状を深く知ることになります。
あちこちにシュタージ(密告者)がいて、住民どうしが監視しあっていること。ひとたび反体制派の烙印を押されてしまうと、職を失い、路頭に迷ってしまうということ。
そして、東ドイツから逃れて西へ行きたいと切望する人々がいること。自由を求めたデモが頻発していること。
「いいこと教えてあげる。この国の人間関係って、二つしかないの。仲間か、そうでないか。より正確に言えば、密告しないか、するかよ。」(p.111)
はじめのうちは他人事のように眺めていた眞山ですが、父親の友人ハインツ・ダイメル氏の息子一家と出会ったことで、状況は大きく変わります。
眞山は一家と深く交流を持つようになりますが、ある日彼らの揉め事に巻き込まれたことがきっかけで、自身も東ドイツから「監視」を受ける立場に陥ってしまうのです。
シュタージに悩まされ、いっそう自分の音が分からなくなってしまう眞山。彼のピアノは「精密機械」、技術はあるがつまらない音楽だと言われ、ヴェンツェルには「水みたいな音」と評されていました。
故郷を遠く離れた東ドイツで、「自分の音」を探すため、眞山は悩み苦しみながら進んでいきます。
物語の後半では、東ドイツを取り巻く情勢の移り変わりによって、眞山に関わる人々の人生が激しく翻弄されていく様子が描かれます。
当時の社会情勢がリアルに描き出され、登場人物の過去や背景が絡まりあいながら物語はドラマチックに展開します。
残る者、国を去る者。
どちらが正しく、どちらが卑劣かということはない。それでもやはり、選択をつきつけられた時、誰もが苦しみ、そしてもう一方の道を選んだ者に複雑な思いを抱く。(p.320)
ゆたかな表現で彩られる、音楽ドラマ

本作は音楽小説としての魅力も満載です。バッハやラフマニノフ、ショパンなど、たくさんのクラシック音楽が登場し、美しい筆致で書かれています。
楽曲の演奏シーンは、色彩ゆたかな比喩表現で迸るように描写されていき、まるでその場で聴いているかのような錯覚も起こします。
物語の中に登場する架空の楽曲ですら、その調べが聞こえてきそうなほどです。
音楽を通して語られる東ドイツの歴史と、そこに生きる人々の人生は、確かなリアリティを持っています。
物語の冒頭、眞山の隣人であるファイネンさんが語る、戦禍を受けて灰となったドレスデンの街が、音楽とともに復興していく様子。
その台詞から、東ドイツに息づく、人々の音楽への愛情がひしひしと伝わってきます。
今なお残る瓦礫の上に、人々は花を捧げる。不思議な光景だった。黒くくすんだ破壊と、溢れる命の色彩と。ファイネンさんは、僕の愛する音楽はこの暗さの中から生まれたと言った。この相反するものから。
音楽に国境はないという言葉は、嘘だ。音楽ほど地域性、国民性が出るものはない。(p.48)
物語が進むにつれ、激動の社会情勢の中、音楽家である登場人物たちも選択を迫られることになります。
音楽を愛するがゆえに難しい決断を下さなければならない、その切実さが胸に迫ります。
「歴史」が好きな人、「音楽」が好きな人、どちらにもおすすめ

著者の須賀しのぶさんは、少女小説出身で、現在は一般小説を書いている作家ですが、少女小説を書いていた頃から骨太なテーマを扱っていたことで知られています。
一般小説では、太平洋戦争の頃を舞台とした『紺碧の果てを見よ』や、ナチス・ドイツを扱った『神の棘』などの歴史ものの小説で評価が高く、『革命前夜』も著者の得意分野と言えるでしょう。
加えて、歴史ものとしてだけではなく、音楽小説としても良質な作品に仕上がっています。
主人公がスランプに悩みながらも、自分の音楽を求めて成長していく姿は、青春小説のような趣も感じられますよ。
歴史エンターテイメント小説が好きな方、クラシック音楽が好きな方、ドイツに興味のある方など、幅広い層の方におすすめできる作品です。
【おすすめ記事】佐渡裕『棒を振る人生』から見える指揮者の仕事
今回ご紹介した書籍
『革命前夜』
須賀しのぶ(著)、文藝春秋