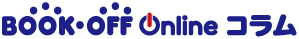欧米話題の“未読書コメント術”「読んでいない本について堂々と語る方法」

『読んでいない本について堂々と語る方法』
ピエール・バイヤール/著 大浦康介/訳 、筑摩書房
みなさんは、友人との会話や学校の授業、職場などで、自分が読んでいない本について、「あの本読んだ?」「どう思った?」と聞かれたことはないでしょうか。
その本が有名だったり、「必読書」と言われていたりすれば、読んでいないことに焦りや罪悪感を感じたりすることもあることでしょう。
そんな経験のある方におすすめしたい1冊が、今回ご紹介する「読んでいない本について堂々と語る方法」です。
読書における「3つの規範」からの解放

著者によれば、読書には3つの規範があるといいます。
1つは「読書義務=神聖とされる本は必ず読んでいなければならない」というものです。
もう1つは「通読義務=本は最後まで読んでいなければならない」ということ。
そして最後の1つが「本について語るためには、その本を読んでいなくてはならない」ということです。
この規範が強固であるがために、人はある本を「読んでいない」ということにやましさを感じてしまうのです。
この本の目的は、そのようなやましさを解消することにあると著者はいいます。そして、小説や映画のエピソードや実例をまじえながら、「未読本」をめぐる考察をしていきます。
「全体の見晴らし」を得る

まず第1章では、「未読の諸段階」と題して、
・ぜんぜん読んだことのない本
・流し読みをしたことのある本
・人から聞いたことのある本
・読んだことはあるが忘れてしまった本
の4つを解説しています。
この章のなかで著者は、「本」は独立して存在しているものではないということを示します。
「ぜんぜん読んだことのない本」の例として、小説『特性のない男』に出てくる図書館司書のムージルが挙げられています。彼は図書館の蔵書を一切読みませんが、そのことによって「全体の見晴らし」を得ることができたといいます。
教養ある人間が知ろうとつとめるべきは、さまざまな書物のあいだの「連絡」や「接続」であって、個別の書物ではない。(p.23)
そして、このように「連絡」や「接続」された本のひとまとまりのことを、著者は、<共有図書館>と呼びます。教養とは、ある本を<共有図書館>の中に位置付け、そして書物の内部で自己の位置を知ることができる能力だといいます。
「本を知らない」ゆえに「独創的な解釈」ができることがある

第2章では、未読本についてコメントする具体的な状況を挙げていきます。
まず、「大勢の人の前で」という状況では、小説『第三の男』に出てくるマーティンズという作家が例に挙げられています。
彼は、西部ものを書いている大衆作家ですが、ひょんなことから、同じペンネームを持つ文学の大作家と混同され、講演会をする羽目になってしまいます。聴衆から文学についてコメントを求められるマーティンズですが、彼と聴衆たちのやりとりは噛み合わず、ちぐはぐになってしまいます。
人びとは、自分の中に<内なる図書館>を持っています。聴衆とマーティンズのやりとりが噛み合わないのは、それぞれの<内なる図書館>が対立し、衝突を起こしているからです。
「教師の面前で」という状況では、人類学者ローラ・ボナハンの例が挙げられます。彼女はハムレットをアフリカのティヴ族に聞かせますが、亡霊を信じない彼らは「死者が歩く」という考えを受け容れられません。
著者は、個人や集団は<内なる書物>をもっていて、新しい本が与えられた時、いつもその<内なる書物>を通して理解をしているといいます。ティヴ族の<内なる書物>には、ボナハンのそれと違って、亡霊という概念がないのです。
つまり、ある本に関する議論とは、お互いの<内なる書物>について議論するということであり、その本を直接知らなくともよく、むしろ知らないほうが独創的な解釈ができることさえあるのです。
未読本の批評を「創造的プロセス」の中に置く

では、実際に未読本について語る時、どんな心がまえを持てばいいのでしょうか。
著者は第3章で、『吾輩は猫である』に登場する、人をかつぐのが大好きな美学者の例を解説しています。
この美学者はある日、とある文学者に、「セオファーノ」という小説で女主人公が死ぬシーンについて話します。文学者も「あすこは実に名文だった」と応じるのですが、実は美学者はこの小説を読んでいません。「女主人公が死ぬ」というのは作り話なのです。それに応じてしまった文学者もまた、「セオファーノ」を読んでいない、ということになります。
しかし著者は、人が本を「読んだ」というとき、それは非常に曖昧なものであると言います。読書には必ず「忘却のプロセス」が働くからです。この文学者も、本当に「セオファーノ」を読んでいないのか、記憶違いをしているだけなのかを知るすべはありません。
そしてこの曖昧さこそが、未読本についての批評を「創造的プロセス」の中に置くことを可能にしてくれるものだと著者はいいます。
というのも、この言説は、それを実践する者に自己と書物が袂を分かつ最初の瞬間を経験させることによって、創造主体の誕生に立ち会わせるからである。そこでは読者は、他人の言葉の重圧からついに解放されて、自己のうちに独自のテクストを創出する力を見出す。こうして彼はみずから作家となるのである。(p.213)
まとめ
私自身、「本当に本を読まなくても批評ができるの?」という疑いの目と、ちょっとした不純な動機でこの本を手にしたのですが、読めば読むほど「本を批評する」ということにおける「創造性」の重要さを知ることになりました。
そして、本について人と語り合うという行為の背景にある、<共有図書館>や<内なる図書館>、<内なる書物>の深遠さにも気づかされます。
著者は、過剰な読書が招く弊害についても語っています。受け身な読書はときには毒となってしまうということを肝に銘じて、いつも創造的な態度を忘れずにいることが肝要のようです。
■今回ご紹介した本
『読んでいない本について堂々と語る方法』
ピエール・バイヤール/著 大浦康介/訳 、筑摩書房