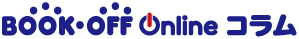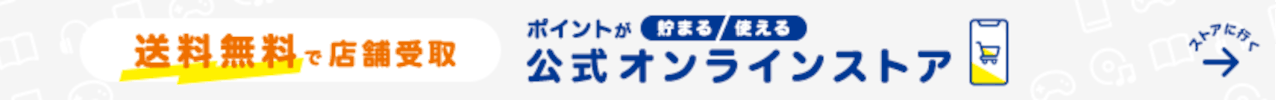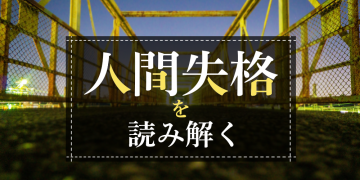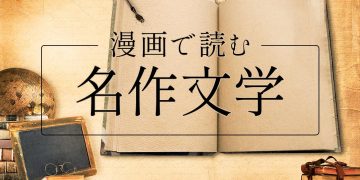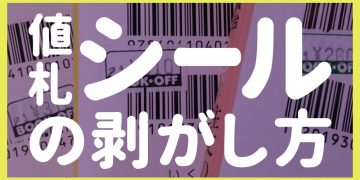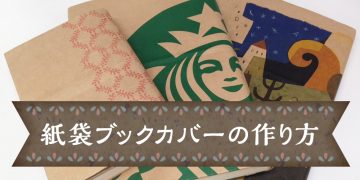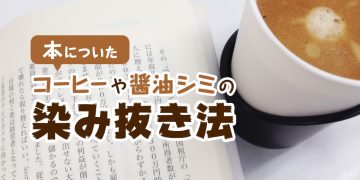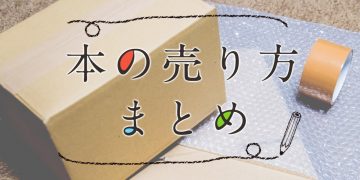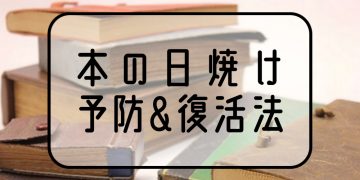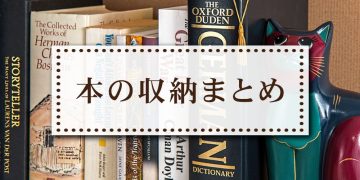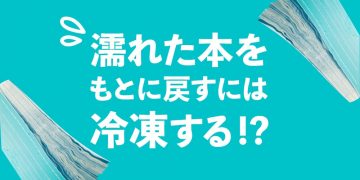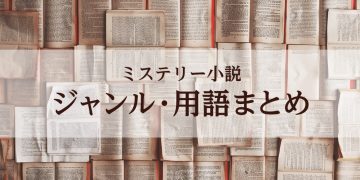宮沢賢治『フランドン農学校の豚』とは? 冒頭がない隠れた名作
更新日:2017/12/13
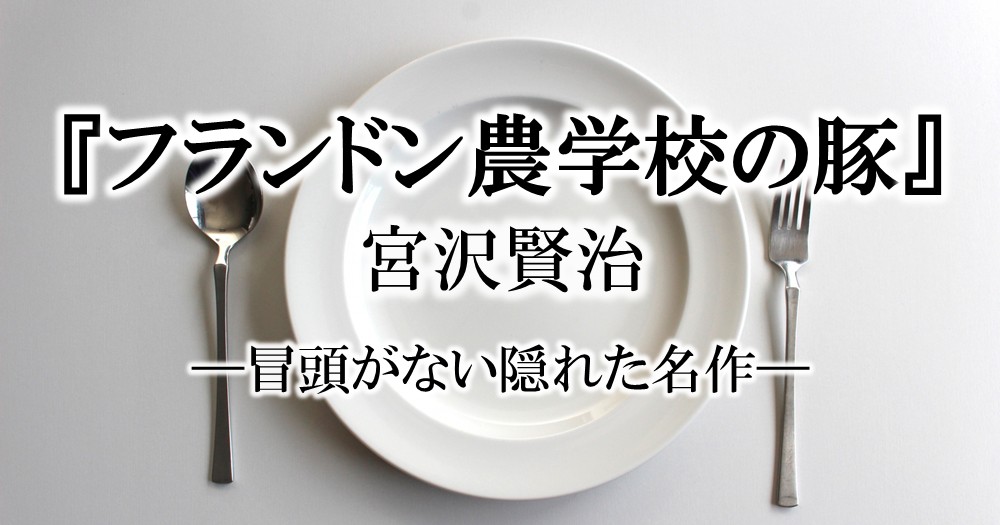
こんにちは、文学好きのアオノです。
突然ですがみなさん、豚肉は好きですか? わたしは大好きです。美味しいですよね、とんかつとか、生姜焼きとか。
さて、豚肉のお話をした今回は、宮沢賢治が書いたとある豚のお話をご紹介します。(唐突!)
『フランドン農学校の豚』とは
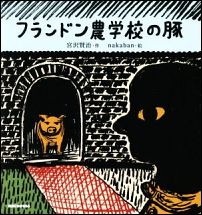
『フランドン農学校の豚』
宮沢賢治(著)、 三起商行
~あらすじ~
フランドン王国で「家畜撲殺同意調印法」が発令された。それは、家畜を屠殺(とさつ)する前に、家畜から「死亡承諾書」を取らなくてはいけないというもの。
フランドン農学校で飼われていた豚は、いつか殺されることを知りながら、承諾書に判を押すことに……。
あらすじを読んだだけでもなんだか哀しいですね……。本作を一言でいうと「豚が屠殺されるまでのお話」。つまり、豚が食肉になるために殺されるまでのお話です。
「命を大切に食べる」という食育にも通じるお話になっていますが、ただの「食育」の話ではないところが『フランドン農学校の豚』の面白いところ。
またこのお話、なんと冒頭がありません。消失しているのです。
賢治が亡くなった後に出版された作品で、タイトルも全集の編集者によってつけられました。途中から始まるアンバランスさが、わたしにはたまらなく魅力的に感じられます。
オリジナルのタイトルがわからない、冒頭もない、けれど確かに賢治の物語で、わたしは隠れた名作だと思っています。
さて、それではこの豚には、どのような運命が待ち受けているのでしょうか?
「死亡承諾書」に印を押す恐怖とは

まず『フランドン農学校の豚』の恐ろしいところは、豚が「自分がいつか殺されて食肉になる」とわかっていながら、承諾書に印を押すことを迫られるところです。
自分だったら、とぞっとしますよね。夢に出てきそうなシチュエーションです。
農学校の校長は「どうせみんないつかは死ぬんだから印を押せ」と言うのです。さらには、豚の体は学校のおかげでできたんだ、と恩に着せるわけです。
想像してみてください。それに印を押すということは「いつでも殺していいですよ」と言っているようなもの。そんな承諾書、印を押せるわけないですよね。
わたしたちだって、先の嫌な予定がわかっていたら、毎日憂鬱に過ごすことでしょう。
そんな些細なことでも気分が落ち込むのに、豚は【死】を目の前にしているのです。自分がいつか殺されるとわかっていながら育てられることが、どれほどの恐怖なのか、想像を絶しますよね。
そして豚は、その恐怖に押しつぶされ、いやだいやだと言いながら、殺される日を待つしかありません。
さらに悲劇的なのは、フランドン農学校の豚は人の言葉を理解し、人の言葉を喋ることができるということ。
さて、それがなぜ悲劇なのでしょうか?
一歩引いて見た「フランドン農学校」と「豚」

本書のすごいところは、豚の気持ちを描きながら、今起こっている事実が淡々と描かれていくところです。
豚は人の言葉がわかるので、農学校側が早く自分を殺したがっていることを、会話を聞いて知ってしまいます。
殺される恐怖におびえる豚と、早く豚を食肉にしたい農学校の様子が、賢治の独特の言葉のリズムで綴られていきます。
どこか一歩引いた目線から、豚と農学校の様子が描かれているため、恐ろしい光景を読みながらも、おとぎ話を読んでいるような気持ちにすらなるのです。
本作は、宮沢賢治作品のなかでも、とても残酷なお話の部類に入る作品です。
『フランドン農学校の豚』はなぜ書かれた?
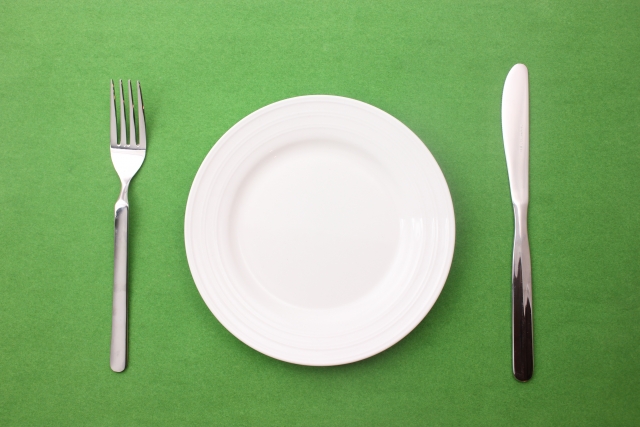
賢治は過去に花巻農学校で教師をしていました。教師時代に、農学校の収穫祭で、同じように豚を殺したことがあるそうです。その経験から、動物を殺して「命を食べる」ことについての残酷性を描いたのでしょう。
また、賢治は菜食主義を貫いていた時期がありました。そんな賢治からの「もっと感謝して食べなさい」という強いメッセージも感じます。
わたしは豚肉も好きだし、牛肉も鶏肉も大好きです。もちろん魚も大好き。
毎日の食事が「命を食べる」ことだとわかっていても、つい「命を食べる」ことがどういうことか、忘れてしまいがちになるのではないでしょうか。
『フランドン農学校の豚』を読むと、そのことをはっと思い出させてくれて、もっともっと生きるために食べる「命」に感謝をしなければいけないなと感じます。
本書は、豚があまりに残酷な経過をたどることで、わたしたちが「食べる」ことへと繋がっていくことを思い出させてくれるお話なのです。
「命を食べる」ということ
文中にこんな言葉が出てきます。
一体この物語は、あんまり哀れ過ぎるのだ。
あまりに哀れで残酷な賢治の物語。ですが「命を食べる」ことについて今一度考えさせられる作品です。
フランドン農学校の豚は、どのような終わりを迎えるのでしょうか。ぜひ読んでみてくださいね。
【関連記事】宮沢賢治の読んでおきたいおすすめ作品
今回ご紹介した書籍
『フランドン農学校の豚』
宮沢賢治(著)、 三起商行
宮沢賢治をはじめ、計23人の文豪の著書をご紹介!